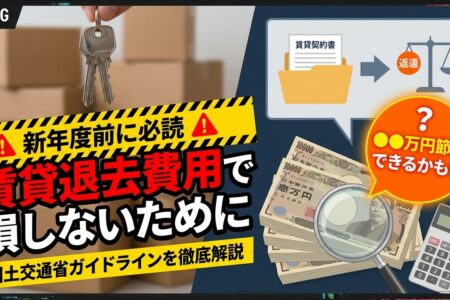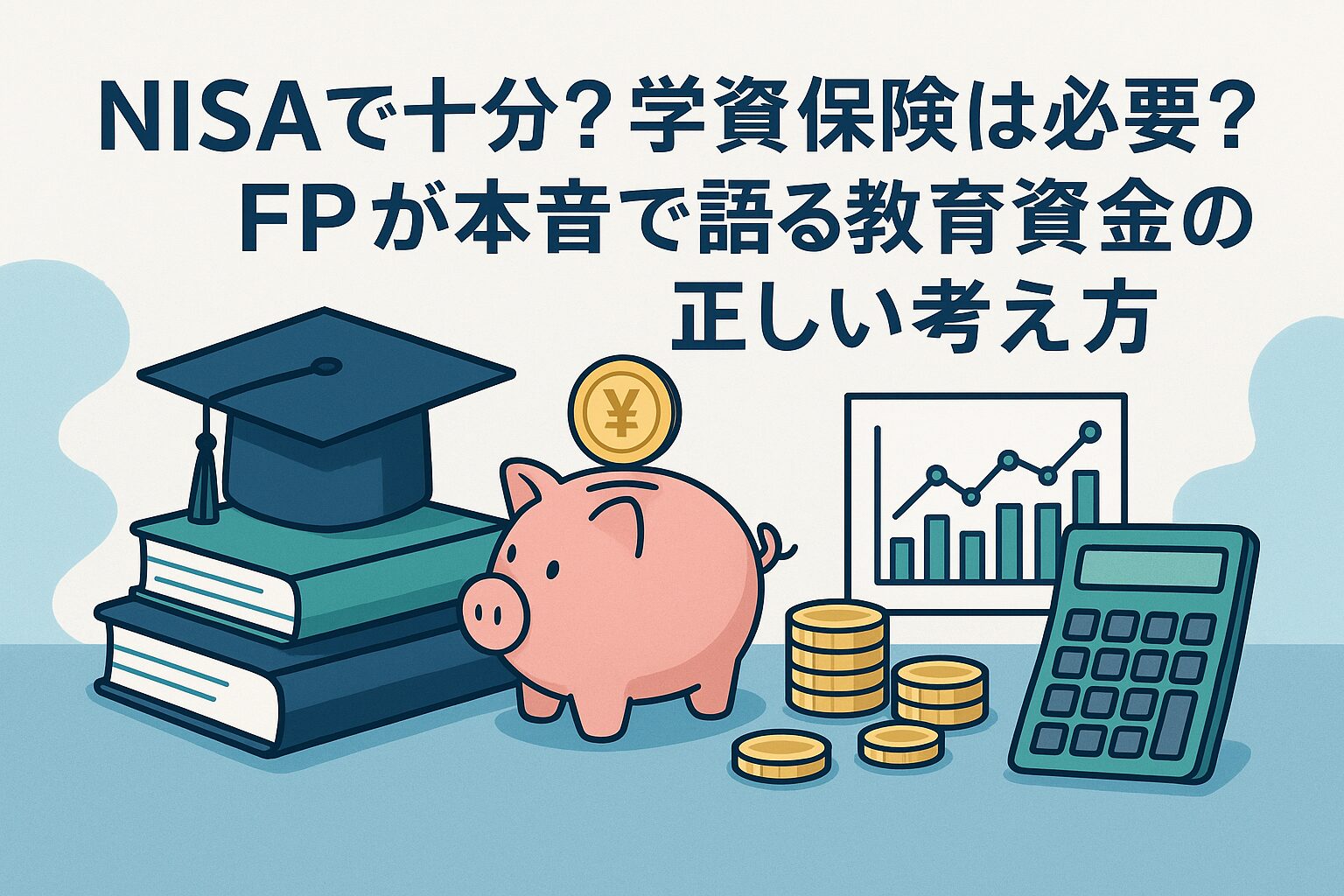
「子どもの教育資金って、どれくらい準備すればいいの?」
お金の相談にのっていると、必ずといっていいほど出てくる質問です。実際に文部科学省の調査によると、幼稚園から大学卒業までにかかる教育費の総額は1人あたりおよそ1,000万〜2,500万円。しかも、大学までオール私立だと2,500万円超という試算もあります。
…数字を見ただけで、「うちの家計でそんなに貯められるの?」と不安になった方、多いのではないでしょうか?
そして、この話題になると必ず出てくるのが「学資保険」と「NISA(少額投資非課税制度)」。ThreadsやSNSを見ても、
- 「やっぱり学資保険は安心!」
- 「いやいや、NISAで十分!」
- 「そもそも何もやってない…」
と、意見が真っ二つ。これだけ情報が飛び交うと、逆に「結局どっちがいいの?」と混乱してしまいますよね。
結論から言えば、教育資金の正解は人によって違うんです。家計の状況、価値観、将来叶えたいライフスタイル――この条件が違えば、選ぶべき方法も変わります。
とはいえ、「人によって違う」と言われても、「じゃあ、どう考えればいいの?」というのが本音だと思います。そこで今回は、FPの立場から学資保険とNISAを本音で比較しつつ、教育資金戦略をどう立てればいいのかを楽しく、でもちょっと本気で語っていきます。
目次
1.教育資金っていくら必要?リアルな数字と家庭の悩み
まず最初に確認しておきたいのが「教育資金ってそもそもいくら必要なの?」という話。これが分からないと、学資保険に入るべきか、NISAで積み立てるべきかの判断材料がなくなってしまいます。
よく「教育費は1人につき1,000万円」と言われますが、それって本当なの? どの家庭でも1,000万円を準備しなきゃいけないの? そんな疑問を、まずはデータで整理してみましょう。
公立と私立でここまで違う!教育費の平均額
文部科学省「子供の学習費調査」(2022年)によると、幼稚園から高校までの学費総額は以下の通りです。
- すべて公立:約540万円
- すべて私立:約1,830万円
さらに、大学費用を加えると…
- 国公立大学(自宅通学):約520万円
- 私立大学(自宅外):約1,000万円超
つまり、幼稚園から大学卒業までトータルで、オール公立なら約1,000万円、オール私立なら2,500万円前後がかかるというわけです。
実際の家庭の声:「そんなに貯められない…」
ここでよくある悩みが、
- 「2人子どもがいたら×2で、2,000万円以上!?」
- 「住宅ローンや老後資金もあるのに、現実的じゃない」
- 「周りの家庭はどうやって貯めてるの?」
というもの。実際、金融広報中央委員会のアンケート(家計の金融行動に関する世論調査)では、教育資金を十分に準備できている家庭は約3割にとどまるというデータも出ています。
つまり、教育資金は「平均○○万円」と一律に語られるけれど、実際には家庭ごとに大きく違うのが現実。だからこそ、学資保険にするか、NISAで積み立てるか――正解は一つじゃないのです。
2.学資保険はアリ?ナシ?本音でメリット・デメリット解説
教育資金の話になると、まず名前が挙がるのが「学資保険」。一昔前までは、「子どもが生まれたら学資保険」というのが定番でした。実際、私自身もFPの仕事を始めたばかりのころ、相談者の多くが「学資保険に入ってます」と答えていました。
でも最近は、SNSでも「学資保険はもう古い」「効率悪すぎ」との声が増えてきています。では、実際のところどうなのでしょうか?本音ベースでメリットとデメリットを整理してみましょう。
学資保険のメリット
- 万が一のときの保障がある
契約者(親)に万が一のことがあっても、その後の保険料は免除され、満期時には予定通りの学資金が受け取れる仕組み。子どもが小さいうちの不安を考えると、この安心感は大きいです。 - 出口の金額が見えやすい
「18歳の時に200万円」といったように、将来の受け取り額がはっきりしているのが特徴。投資のように「増えるか減るか分からない」という不安がなく、計画が立てやすいのもメリットです。
学資保険のデメリット
- 運用効率が悪すぎる
実際にシミュレーションしてみると、返戻率はせいぜい102〜105%程度。100万円預けて105万円にしかならないのに、18年も資金がロックされる…これは「効率が悪すぎる」と言わざるを得ません。 - 流動性が低い
一度契約すると、途中で解約すれば大きな元本割れ。急にお金が必要になっても自由に引き出せないのは大きな弱点です。
学資保険は「貯蓄」と「保険」が一緒になった商品ですが、実際にはどちらも中途半端。
- 貯蓄としては効率が悪い
- 保険としては掛け捨て保険のほうが安くて優秀
だから基本的にはおすすめしていません。
ただし、どうしても「減るリスクは絶対に嫌だ」という方にとっては、選択肢として残してもいいでしょう。数字が確実に戻ってくる安心感は、一定の価値がありますから。
3.NISAで教育資金を準備するってどうなの?
一方で最近人気なのが「NISA」。少額から始められる投資で、しかも利益が非課税。ネットや書籍でも「教育資金はNISAで積み立てればOK」といった記事をよく見かけます。
確かにメリットは大きいのですが、気をつけたいポイントもあります。
NISAのメリット
- 効率よく資金を増やせる可能性
たとえば利回り4%で18年間積み立てると、毎月3万円で約880万円に。銀行預金では到底届かない成長が見込めます。 - 流動性が高い
学資保険と違って、必要なときに引き出せるのは大きな安心。 - 運用益が非課税
通常なら20%かかる税金がゼロ。長期投資ではこの差が非常に大きくなります。
NISAのデメリット
- 知識が必要
ファンド選びや運用戦略を間違えると、思ったような成果が出ないことも。 - 暴落時に使えないリスク
「子どもの大学入学金が必要!」というタイミングで暴落していたら…引き出すのに抵抗を感じてしまうリスクがあります。 - メンタルが試される
上がっていても下がっていても、「売ったほうがいいの?」「まだ持つべき?」と常に不安がつきまとうのが投資。
NISAは「効率的に教育資金を準備できる可能性」がある反面、暴落リスクへの備えが必須。
だから「教育資金はNISA一本で!」というのはやや危険です。
現実的には、預金・NISA・掛け捨て保険をうまく組み合わせるのが安心です。
4.「正解は人それぞれ」をどう判断する?FP流の考え方
ここまで「学資保険」と「NISA」を比較しましたが、結局のところ「どっちが正解?」という声が一番多いんです。でも残念ながら、教育資金の答えは一つではありません。
判断の軸はこれ!
- 今の資産状況
毎月どれくらい貯蓄できるか?急な出費に対応できる余力はあるか? - 将来の生活スタイル
「子どもは私立も視野に入れたい」のか、「できれば公立で」と考えているのか。 - リスク許容度
「お金が減るかもしれない」と聞いて眠れなくなる人は、NISAに全力投資は危険。
バランスの考え方
- 安心重視派 → 掛け捨て保険+預金メイン
- 効率重視派 → NISA+一部現金確保
- その中間 → 預金・NISA・掛け捨てをバランスよく
FPとしては、この「バランスをどう取るか」を一緒に考えるのが一番大事だと思っています。
5.広島・岡山のご家庭からの相談事例
実際に私が相談を受けるのは、広島や岡山のパパ・ママが多いです。地域性もあり、「教育資金どうしよう?」という悩みはどの家庭も共通しています。
事例1:広島市のご家庭
住宅ローン+2人の子ども。学資保険に入っていたが、「増えないこと」に疑問を感じて相談。結果、掛け捨て保険で保障を確保し、NISAに切り替え。資産効率が大幅に改善。
事例2:岡山市のご家庭
「投資は怖い」との理由で貯金のみ。FP相談を経て、教育資金の半分はNISA、半分は定期預金に分散。心理的な安心と効率を両立できた。
6.教育資金は「安心」と「効率」のバランスで考えよう
教育資金の準備には「学資保険」と「NISA」という代表的な選択肢がありますが、どちらも完璧な正解ではありません。
- 学資保険 → 安心だけど効率が悪い
- NISA → 効率的だけど不安定
だからこそ、家庭の状況に合わせて「ちょうどいいバランス」を見つけることが重要です。
この記事を読んで「なるほど、でも我が家の場合はどうすればいいの?」と感じた方。まさにそこがFPの出番です。
広島・岡山で教育資金の準備に悩んでいるパパ・ママ。よければ一度、気軽にご相談ください。数字だけじゃなく、ご家庭の未来や価値観に合わせた最適なプランを一緒に考えましょう!
\無料相談受付中✨/
SOUKAでは無料でのFP相談を受け付けています!
広島、岡山を中心に、全国のお客様をサポート!
公式LINEもしくはHP内の問い合わせフォームからご連絡ください!
まずはオンラインでお気軽にご相談ください!
公式LINE:https://lin.ee/A6gc2oZ
問い合わせフォーム:https://souka-futa.com/contact/
出典一覧
文部科学省「子供の学習費調査」(2022年)
金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」(2023年)
各社学資保険ランキング(価格.com、保険市場 2025年9月時点)